

3.線形補間(拡大、縮小)
ここでは、補間のうち、線形補間の計算式を導出する方法を示します。
画像補間の方法として、線形補間法を用いている。この式は以下の形式となる。
1.理論式
以下に補間式を示す。
![]() 式
(1)
式
(1)
ここで、Kp1及びKp2の係数はa/bという分数の形をとっている。
Kp1やKp2といった係数の求め方を考える。
これには、補間方法のひとつである、ルグランジュ補間法を用いる。以下にルグランジュ補間式を定義する。
![]() 式 (2)
式 (2)
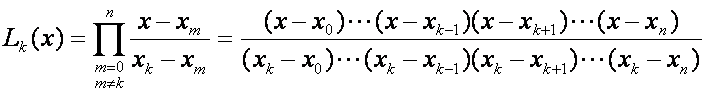 式
(3)
式
(3)
f(Xk)は補間する点の画素の明るさで、Xkが位置である。
以下に例をあげる。
例):n=1の時。つまり、式(2)から2画素の場合と考える
![]()
![]() 式(4)-1,(4)-2
式(4)-1,(4)-2
![]() 式(5)
式(5)
では、画素間を補間する場合を考える。補間に使用する点を2画素とする。すると、式(4)のn=1
の場合である。
ここで、X0,X1は画素でその位置を表しており、その間隔は1である。よってこの式は、
X0=0,X1=1の時つまり、上記の式がk=0,n=1のとき
![]()
X1=1,X2=2の時つまり、上記の式がk=1,n=2のとき
![]()
では、一般化して、k=nの時はつまり下記の時、
![]() のとき、補間後の画素の位置をx、画素の明るさをP(x)とする。XnとXn+1は原画像の位置である。
のとき、補間後の画素の位置をx、画素の明るさをP(x)とする。XnとXn+1は原画像の位置である。
![]() 式(6)
式(6)
ここで、画素を拡大する場合の拡大の考え方は、以下の通りである。
わかりやすく、具体例を用いて説明すると、
拡大率が4/3倍を考える。
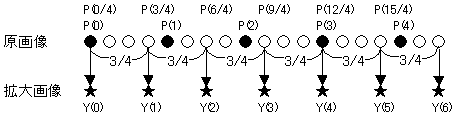
●---原画像の画素、I(n)
★---拡大後の画素、P(x)
この考え方は、原画像の1区間を4等分して、そのうちの3つ目を新たな画素とする。
つまり、3/4づつ再サンプリングを行う。拡大後の画像と原画像を対比させると、
Y(0)=P(0/4)=P(0)
Y(1)=P(3/4)
Y(2)=P(6/4)
Y(3)=P(9/4)
Y(4)=P(12/4)=P(3)
となる。このY(x)をP(x)から導くときに用いるのが、(6)式である。
ここで、Xnのnの条件について考える。Xnは原画の位置である。つまり、補間の元になるデータである。
上記図から補間される画素の位置XはXn<X<Xn+1である。よって、XがXn+1を超えた時、nは1増えるとする。
上記nの条件と(6)式から
![]()
![]()
ここで、X1<6/4となる為、nはひとつ増える。
![]()
ここで、X2<9/4となる為、nはひとつ増える。
![]()
ここで、X3<12/4となる為、nはひとつ増える。
![]()
以下これの繰り返しとなる。
以上は、原画の2点を用いた補間である。n=1の時。これは、2次方程式である。
これを拡張していくと、n=2の時は2次方程式となり、n=3では3次方程式となる。